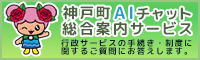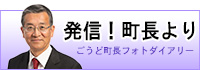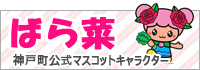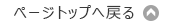国民健康保険
病気やけがをしたとき、安心してお医者さんにかかれるよう、加入者が保険税を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費にあてる助け合いの制度です。
わが国では、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。
国民健康保険(国保)には、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除くすべての人が加入します。
国保に入るのはこんな人です
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業を営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- 健康保険の扶養からはずれた人
- パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
国保では一人ひとりが被保険者です
国保では未成年者や幼児、世帯主や家族の区別なく、みんなが平等に加入します。
加入は世帯ごとに行います
世帯主がまとめて加入手続きを行い、一人に1枚の資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。
国民健康保険税についてはこちら
国保に加入する日・やめる日
以下のときは、14日以内に届け出をしましょう。
加入する日(国保の資格が発生する日)
- 他の市区町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
- 子どもが生まれた日(自営業などの人)
- 生活保護を受けなくなった日
やめる日(国保の資格がなくなる日)
- 他の市区町村へ転出した日の翌日、またはその日
- 職場の健康保険などに加入した日の翌日
- 死亡した日の翌日
- 生活保護を受け始めた日
届け出に必要なもの
加入する場合
- 職場の健康保険をやめた日か扶養がはずれた日がわかる証明書(健康保険資格喪失連絡票)
注)扶養家族がいないときは、離職票や退職証明書でも手続きができます - マイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※勤務先や加入していた健康保険組合で発行してもらってください。書式は任意です。所定の様式がない場合には健康保険資格取得・喪失連絡票様式をご利用ください。
脱退する場合
- 新しく交付された職場の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 交付されていた国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※別世帯の人が手続きをする際には、委任状が必要です。
高額医療費支給制度
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
高額療養費に該当する人は、病院へかかった月の2ヶ月後以降に、役場から文書等で案内いたします。
申請に必要なもの
- 病院等の領収書
- 振込先のわかるもの
- 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 来方される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
高額医療費の算定方法
- 月の1日から末日までの受診について1ヶ月として計算します。たとえば、当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2ヶ月の計算となり合算することはできません。
- 一人の人が一つの医療機関でかかった一部負担金を合計して計算します。 (歯科・入院・外来は別計算)
- 70歳未満の人については、同じ月内に同じ世帯で1件21,000円以上の一部負担金が2件以上あった場合にはその一部負担金を合算できます。
- 70歳から74歳の人については、すべての一部負担金が合算できます。
- 保険適用外のものや、食事代、差額ベッド代等は含みません。
70歳から74歳の人の自己負担限度額
| 区分 (所得区分の目安) |
自己負担 割合 |
1ヶ月の自己負担限度額 (3回目まで) |
多数該当 ※1(4回目から) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来 | 入院(世帯合算) | 入院(世帯合算) | |||
| 現役並み所得世帯 (住民税課税世帯) |
(Ⅲ)課税所得 690万円以上 |
3割 | 252,600円 保険医療機関の総額が842,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 |
140,100円 | |
| (Ⅱ)課税所得 380万円以上690万円未満 |
167,400円 保険医療機関の総額が558,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 |
93,000円 | |||
| (Ⅰ)課税所得 145万円以上380万円未満 |
80,100円 保険医療機関の総額が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 |
44,400円 | |||
| 一般世帯 (課税所得145万円未満) |
2割 | 18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
| 住民税 非課税世帯 |
低所得Ⅱ | 8,000円 (年間限度額144,000円) |
24,600円 | ||
| 低所得Ⅰ | 15,000円 | ||||
70歳未満の人の自己負担限度額
| 区分 (所得区分の目安) |
自己負担 割合 |
1ヶ月の自己負担 限度額(3回目まで) |
多数該当※2 (4回目から) |
|---|---|---|---|
| 基礎控除後の総所得金額等が 901万円を超える世帯 |
3割 | 252,600円 保険医療費の総額が842,000円を超えたときは超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
| 基礎控除後の総所得金額等が 600万円を超え 901万円以下の世帯 |
167,400円 保険医療費の総額が558,000円を超えたときは超えた分の1%を加算 |
93,000円 | |
| 基礎控除後の総所得金額等が 210万円を超え 600万円以下の世帯 |
80,100円 保険医療費の総額が267,000円を超えたときは超えた分の1%を加算 |
44,400円 | |
| 基礎控除後の総所得金額等が 210万円以下の世帯 |
57,600円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 同じ世帯で、診療を受けた月(その月を含む)以前12ヶ月に、既に3回高額療養費の支給を受けた場合は、自己負担限度額がこちらの金額になります。70歳未満と70歳から74歳の人が同じ世帯の場合、まず70歳以上の人だけで計算します。次に、その結果に70歳未満の合算対象分を加えた後70歳未満の自己負担限度額を用いて計算します。
高額療養費支給申請手続の簡素化について
高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請が必要ですが、令和5年10月以降の申請分から、支給申請簡素化の手続きをすることで、次回以降の申請が不要となり、指定された口座に自動振込とすることができます。
簡素化を希望される方は、令和5年10月以降に高額療養費に該当した場合に支給申請書と一緒に「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書」(以下「簡素化申請書」という。)を提出してください。
簡素化の対象世帯
以下の要件をすべて満たす世帯です。
- 国民健康保険税の滞納がない世帯
- 「簡素化申請書」に記載する同意事項に同意した世帯
申請に必要なもの
(参考)
国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書(別紙様式)(記入例)(PDF)
簡素化の解除について
次のような場合は、簡素化が自動的に解除となり、高額療養費に該当した場合は申請案内を送付いたしますので、支給申請手続を行ってください。
簡素化の解除後に再度簡素化を希望される場合は、簡素化申請書の再提出が必要です。
- 世帯主が変更した場合
- 国民健康保険被保険者記号番号が変更になった場合
- 指定した振込先金融機関口座に振込ができなくなった場合
- 国民健康保険税の滞納が発生した場合
注意事項
- 簡素化を申請した翌月以降、高額療養費に該当した場合は、自動的にご指定の口座に振込がされます。入金日及び入金額は、「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」にてご確認ください。
- 簡素化の申請以降は、支給申請についてのお知らせは送付されません。
- 振込先口座は、1世帯につき1口座のみです。被保険者ごとの振込口座の分割や月ごとの変更はできません。
- 振込先口座の変更、簡素化の解除を希望される場合は、簡素化申請書の提出が必要です。
- 既に高額療養費支給申請のお知らせが発行されているものについては、簡素化対象となりません。未申請の場合は、申請していただきますようお願いします。
限度額適用認定証
医療費(保険診療分)が高額になる場合は、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方はあらかじめ医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示すると1ヶ月に1医療機関に支払う一部負担金が自己負担限度額までになります。
申請には以下のすべてに該当する事が必要です。
- 国民健康保険税を納付し、滞納がないこと
- 交通事故等第三者の不法行為でないこと
※70歳以上75歳未満で、所得区分が現役並み所得者Ⅲ・一般の人は、資格確認書を提示することで、医療費の一部負担金の支払いが自動的に高額療養費の自己負担限度額になるため、「限度額適用認定証」の申請は不要です。
申請に必要なもの
- 世帯主と対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※別世帯の人が手続きをする際には、委任状が必要です。
注意事項
- 保険料に滞納がある世帯(分割納付中も含む)や、納付実績のない世帯については申請することができません。
- 世帯の中に前年(または前々年)所得が不明の人がいる場合、所得判明後の発行となります。
- 世帯の所得区分が変更になった場合(税の所得修正など)、認定証の区分が変更となるため、再度申請が必要になります。
- 所得判定のため、毎年8月に更新の手続きが必要になります。
療養費の支給
医療機関が治療上必要と認めた補装具を作った場合や、マイナ保険証か資格確認書等を持たないで治療を受けた場合は、審査により必要と認められれば、保険診療による自己負担分を差し引いた金額が支給されます。支給を受けるためには届出が必要です。
届け出に必要なもの
- 療養費支給申請書/PDFファイル
- 領収書
- 医師による証明書(補装具の場合)
- 診療報酬明細書(10割診療の場合)
- 振込先の通帳
※申請内容により必要書類が異なります。詳細については担当課までお尋ねください。
一部負担金の減免制度
災害や事業の休廃止など特別の事情により収入が一定額以下になり、医療機関などに支払う一部負担金の支払いが困難になったとき、減免や支払猶予を一定期間受けられる場合があります。詳細については住民保険課へお問い合わせください。
要件
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し若しくは障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
対象者
(原則次の1~3すべてに該当)
- 一部負担金の支払義務を負う被保険者が属する世帯の世帯主
- 神戸町に6箇月以上住所を有している者
- 減免等の措置を受けようとする世帯に賦課された国民健康保険税を滞納していない者
※ただし、入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯主及び該当世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯、又は特別の事情があると認められる者は、この限りではありません。
期間
申請月から12か月の内3か月
人工透析が必要な「慢性腎不全」、「先天性血液凝固因子障害」と診断された
厚生労働省指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その治療にかかる自己負担額は月額10,000円までとなります。
世帯の収入が上位所得の70歳未満の人で、人工透析治療にかかる自己負担額は、月額20,000円までとなります。
出産育児一時金
国保加入者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
(他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません)
出産育児一時金の金額
50万円(原則)
※48万円8千円+産科医療補償制度対象分娩:1万2千円
直接支払い制度
分娩費用に出産育児一時金を充てることができるよう、出産育児一時金の50万円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は48万8千円)を上限で医療機関へ直接支払うものです。
医療機関と本人との契約となるため、事前に町へ申請する必要はありません。
産科医療補償制度
産科医療補償制度は、分娩を取り扱う病院や診療所などが加入する制度で、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられ、重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられることによって、産科医療の質の向上が図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることを目指しています。
手続き方法
直接支払制度を活用
- 分娩費用が50万円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は48万8千円)以上の方
「出産育児一時金申請書」不要 ※医療機関と本人との契約となります。
- 分娩費用が50万円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は48万8千円)未満の方
「出産育児一時金申請書(金額未記入のもの)」の記入
(添付書類)
- 医療機関の交付する出産費用の領収・明細書の写し(直接支払制度を活用し、請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの)
直接支払制度を活用されない方
「出産育児一時金申請書」
- 医療機関の交付する合意文書の写し(直接支払制度を活用しない旨が記載されているもの)
- 医療機関の交付する出産費用の領収・明細書もしくは請求書の写し
葬祭費
国保加入者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に対して5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- お亡くなりになられた方の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 葬祭を行ったことを証する書類(会葬礼状または申請書名義の葬祭に要した費用の領収書)
- 振込口座の確認できるもの(通帳等)
- 手続きに来られるかたの本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
交通事故にあった場合(第三者行為による傷病届)
交通事故や傷害事件など、他人(第三者)の行為が原因でケガや病気になった場合、加害者が被害者の治療費を負担することが原則ですが、国民健康保険を使用して治療を受けることも可能です。その際には、必ず住民保険課の窓口に届出をしなければなりませんので、ご注意ください。
被害者の医療費は一時的に神戸町が立て替えますが、あとから神戸町が加害者に、過失割合に応じてその立て替え分を請求します。
届け出に必要なもの
- 印鑑
- 事故証明書(未取得の場合は取得次第)
- 各種申請書
※各種申請書は岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページに掲載されています。